
|

|
|
枝川公一氏
|
1940年 東京向島に生まれる。
東京外国語大学英米科卒。ノンフィクション作家。
光文社に5年半勤務後、フリーとなる。
主な著者に『上海読本』『香港読本』『サンフランシスコ旅の雑学ノート』『ジョンレノンを探して』『都市の歩き方』『東京はいつまでも東京でいつづけるのか』『大阪大探検』
近刊『街は国境を超える』(都市出版)がある
|
|
「好きですね」
枝川公一さんの開口一番が、この言葉でした。
「ネオンの人工的な、光。そして色」
「赤とグリーン、ブルーといった単純な色を組み合わせてつくられるネオン。アメリカの、バーの窓辺によくある、“バドワイザー”や“ミラー”といった小さなネオンがとても好きです」
枝川公一さんはノンフィクション作家です。その代表作は『都市の歩き方』(北斗出版)。それで日本のペディストリアンといわれます。
─旅が多い枝川さんが、中でも得意とするのがニューヨークですね。
「アメリカに行くようになってから、ネオンが好きになったかな?ネオンと人間の気分とが同調する。例えば、旅先で車を走らせていて、ちょうど、どこか泊れるところはないかなあと探す頃、遠くにモーテルのネオンが、だんだん見えてくる。その時ですね、気分が同調してくる。70年代の映画『イージーライダー』にそんなシーンがありますね。ピーター・フォンダとその仲間たちが、誰もいない通りをバイクでやってくる。ベイカンシー/ Vacancy(空室あり)と、モーテルの紅いネオンが一つ点いている。“ウエルカム”のサインとわかる、あの気分はとてもよくわかります。それが、No Vacancy(空室なし)/“ノンウエルカム”だと、また探さなくてはならないから、がっかりすることになるんですがね」
─枝川さんが好きなネオンは、アメリカに多いんですか?
「ええ。アメリカにはネオンが定着している。ネオンのショップが大きな町に一つはある。印象的だったのはハリウッドの近くにあるネオン屋です。店内は真っ黒で、ネオンが飾られている。サンプルなんでしょうね。客は色見本のようにして選んで注文できる」
「日本では、ネオン屋さんてどこにあるかわかりませんよね。ネオンを見せてくれるショップがあってもよさそうですが」
─インテリアに使ったりもする?ネオンの使われ方が違いますか?
「日本の場合、ネオンは会社がやる。屋外広告として、大がかりなものですね。アメリカと日本では、ネオンの規模が違うんですね。日本は、会社がやるからお金をかけたわりに個性的になれない」
「そういえば、10年くらい前ですか、ネオンのアーティストに会ったことがあります。店舗設計を主としている人で、ジョーさんと呼んでいましたが、カフェバーの『レッドシューズ』のネオンをつくった話をしていました。その時、東京でネオンを個人でつくっているのは彼だけしかいないと言っていましたね。ネオンの流通が違う。デパートでネオンを売っていてもいいじゃないですか。合羽橋でネオンは売っていないのですか?電気の入っている行灯のようなのは売っていますが」
─昨年は『香港24時』を出されましたね。香港といえば、ネオンは?
「ええ。香港は街自体が発光していて、装飾の中にネオンはあるけれども、目立たない。そういえば、香港島のビクトリアハーバーでは海に向かって立っているネオンは静止していますね。空港が近くにあってネオンを点滅させることができないんですね」
「僕の遠い記憶には、吾妻橋のたもとのアサヒビールのネオンがとても印象的です。子どもの頃、隅田川を渡って東武電車に乗って浅草によく遊びに行きましたが、帰る時にはビール工場のネオンが点る。ブルーの波に太陽。それが川面に浮かんでいるように映る。強烈な印象があるんです。けれども、それは社史にも載っていなくて、今は誰も知らない。僕の中で印象だけが肥大しているのかもしれないんですよね
─単純で古典的なデザインですね。暗くなって帰る気分と、ブルーの波がネオンの光を映した川の流れと一緒に大きく揺れている様子がわかるようです。
「日本では東京のネオンが一番いいですね。地方に行くと貧弱になる。大阪はネオンに力が入っていない」
「大阪は実質的です。僕のネオンのイメージはフランス映画に出てくる、真っ暗闇にぼんやり映る白いネオンです。フランスには行ったことはないんですがね」
「ネオンって、チャーミングでしょ。真直ぐじゃなくて曲がっている」
─枝川さんのネオンのイメージは、言葉で表わすと、蟲惑的ですか?
「いや、セクシーな感じはしない。かわいくて、きれいですよね。ネオンって涼しいでしょ。ネオンは群れない。孤独ですね。それで充足している」
「シンガポール、上海、ソウル、サンフランシスコ、
日本で街の人々は、ひとりひとりバレーを踊っている!」は、昨年、講談社から発売された『シンガポールの街頭理髪店』の帯のコピー。学生時代から始まっている枝川流の旅の仕方は読者を旅する気分に誘います。に太陽。それが川面に浮かんでいるように映る。強烈な印象があるんです。けれども、それは社史にも載っていなくて、今は誰も知らない。僕の中で印象だけが肥大しているのかもしれないんですよね」

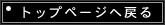

1998 Copyright (c) Japan Sign Association



