
|

|
|
樋口正一郎氏
|
ひぐちしょういちろう
1944年、北海道生まれ。東京芸術大学彫刻科卒。東京大学工学部都市工学科研究生。第9回現代日本美術展コンクール優賞受賞。環境造形の研究の他、彫刻、造形作家、写真家、評論家としても活躍。
|
|
|
樋口さんの造形作品は2000年に開通される都営12号線地下鉄清澄駅の壁面を飾ります。「アート壁デザインパネル」。写真左は銀座の日辰画廊で開催された個展案内状より。写真右は立川ファーレにあるアントナコス氏のネオンアート。
|
 
|
写真展「都市のイルミネーション2」を東京ガスのショールームで開催された樋口正一郎さん。
写真展のサブタイトルは『天使の遊び場』。そこには、昼間雑踏にかき消されている美しい都市の風景があります。また、一昨年開催の「都市のイルミネーション1」のサブタイトルは『光が闇を演出する』と題されています。
─印象的なサブタイトルですね。やはり、イルミネーションは欧米が美しいんですか。きらびやかな都市を彩るイルミネーションを余すことなく見せてくださいました。その中にネオンの光もありますか?
都市は、夜をどういう風に使っているかでその成熟度が分かります。ニューヨークのように、24時間地下鉄が動いているような街は欲望の選択肢が多い。とかく危険な街というイメージが強調されがちですが、向こうは超高層ビルが多いでしょ、どうしても足下が暗いんです。石とコンクリートでできたニューヨークに、街灯よりもっとヒューマンなものが求められて、ネオンアートが出てきたんだと思います。
ネオンアーティストの第一人者のスティーブン・アントナコス氏とは親交があります。彼は60年代末にキネティックアートでスタートしましたが、現在はパブリックアートの分野でも活躍しています。
彼のネオンアートは、生まれ故郷のエーゲ海から太陽が昇ってくるイメージや波のイメージをいつも感じさせます。忘れてしまった永遠を見ることができるというか・・・。
今の都市は自然をどういう風に取り込むかという所では全敗ですよね。まったくうまくいっていない。テキサスのサンアントニオの図書館で、駐車場からホールに行く途中に、アントナコスのネオンアートがあるんですが、ブルーの円弧を描いたアーチが月の光を思わせる。メキシコに近く暑い土地柄で、そこを通ることによってブルーの光のシャワーを浴びたように、熱気を払拭されるような身体的経験をすることができる。
─今まで、ネオンと自然とは対局にあるという意識しかなかったのですが。
ネオンの光の純粋さが疑似自然光を作り出している。ボストンの鉄道と地下鉄の乗換駅にもアントナコスのネオンアートが使われています。やはり、明るい太陽と蒼い海を思わせます。
─アントナコスさんのネオンアートは東京のファーレ立川にもありますね。
ええ、九州にもあります。日本でのアントナコスの作品は、そういう自然を疑似体験できるというような意味ではあまり成功していないと思います。いろいろ制約などあったのではないでしょうか。
─樋口さんは「都市空間にアートを・・・」という世界のパブリックアートの変遷を最初からずっと20年以上見てきていらっしゃる。最近の動向は・・・?
1960年代にアメリカで始まったパブリックアートが瞬く間に世界に広まりました。最近はEU圏の過剰とも思える積極性に比べてアメリカは低調でした。
EU圏の都市は陸続きなので、国境はあっても無いのと同じなんです。人は好きな時に好きな歴史、風物、環境を選択する事ができて、流動的なんですね。数カ国語できたり、単一民族じゃないこともあると思いますが、魅力ある街づくりに、特に過疎地は必死です。フランスとドイツの国境近くにあるストラスブールでは大学やEUのセンターを誘致したりしている。21世紀のビジョンを見据えた都市環境づくりをしている。
アメリカではロサンゼルスの美術館、ゲティセンターで、彫刻家ロバート・アーウィンが手がけた庭は予想を超えてものすごいものでした。水にまつわるさまざまの材料や表現を駆使している。そしてビオトープ風にしつらえた植物の間をそぞろ歩いていると、パブリックアーティストが悩み続けた自然に対する答えを、アーウィンが明快に提示したことを強く感じます。
─ネオンアートの未来もその辺にあるのでしょうか。今日はお忙しいところありがとうございました。

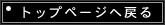

1998 Copyright (c) Japan Sign Association





