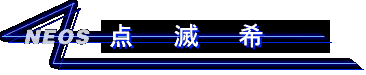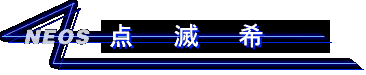| 若い頃、雨が好きですという言葉には嘘があると思っていた。たしかに、部活の練習が軽くなるとか、それなりにいいこともあったが、だからといって、そのことが雨を好きにさせる要素になるかと言えば、そんなことは絶対になかった。
20代の半ば、山にのめり込むようになると、雨は最も嫌いなもののひとつになった。嫌いなものとしての存在感を、はっきりと有するようになっていた。
そんな時だったろうか、地元の兼六園の中にあったお店の軒先で、雨宿りを強いられたことがあった。店はすでに閉められ、内側に白いカーテンが引かれた硝子戸の前に立って、前方の雨に煙る石垣の風景をぼんやりと眺めていた。
時折、庇から水滴が落ちてくる。何度かそれを見ているうちに、その水滴が気になり始めた。水滴は地面にできた、小さな水たまりへと落ちていく。
夕暮れ時…、新緑が雨に濡れ、薄く明りを反射させている。そして、雨の音の中に水滴の音が絡む。雨の匂いが夕暮れとともに消えていったような気がした。
そして、ふとあることを思い出した。大学時代の日本文学の先生が語っていた、“日本の雨”という話だ。日本らしい雨の風景を、まだ日本の作家は書き切れていないと、先生は力説していた。
大学を卒業してまだ三年ほどしか過ぎていない、梅雨どきのある日のことだった。あれ以来、毎年梅雨が訪れると、その話を思い出すのである………。
|