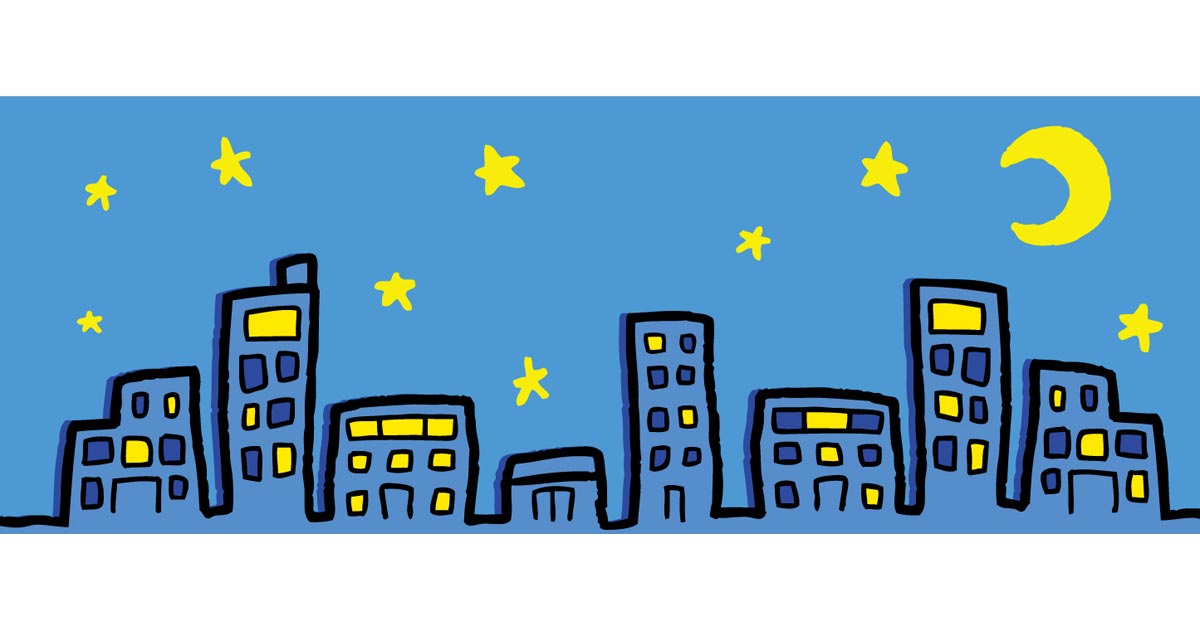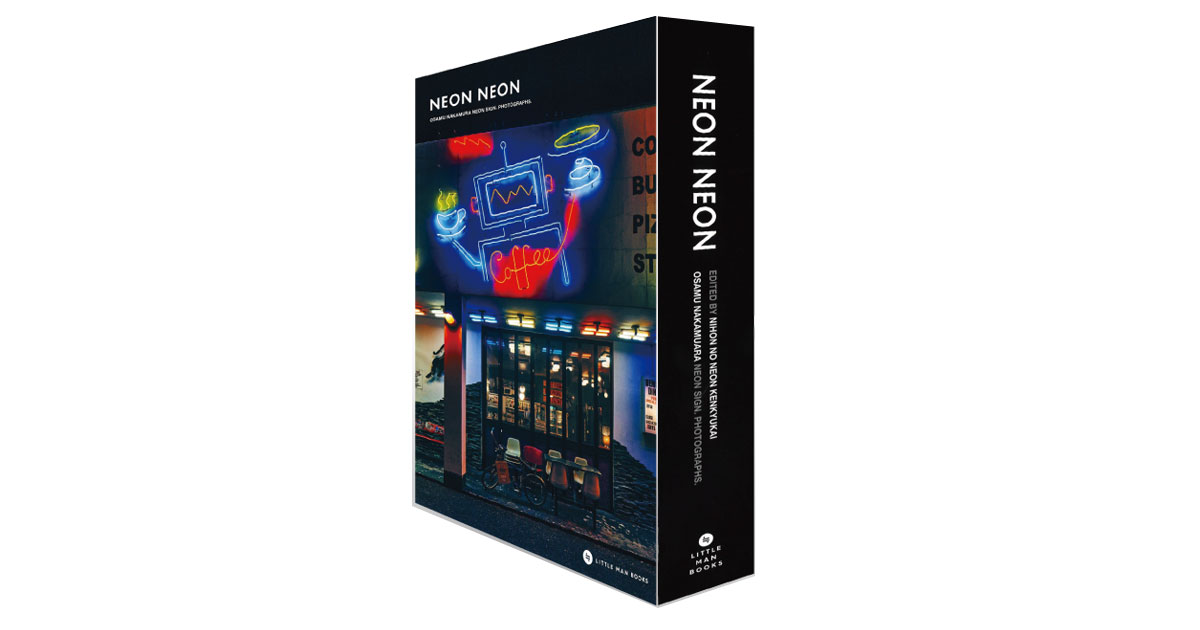高橋昌男(作家)
〈角筈一丁目一番地〉の副題をもつ自伝的青春小説『ネオンとこおろぎ』(新潮社)を本にしている。終戦の翌々年、11歳の春から23年間そこで暮らした新宿三越裏での私の内面の成長記録というべきものだが、私の成長に合わせて、戦後の文化現象の象徴ともいうべき新宿という街の移り変わりが丹念に描かれている。
私の精神形成に与って力のあった新宿なるトポス(場所)に赤、青、緑、ピンクのどぎついネオンサインは欠かせない。母が小商いをしていた裏通りの斜め向かいにサロン銀河というカフェーがあったけれど、上部の外壁いっぱい、青やピンクの星型が点滅する図はいっそ感動的であった。
本にも書いたのだが、ネオンが新宿の夜をいろどったのは朝鮮戦争のさなか、昭和26(1951)年の秋頃からと思われる。それより以前のいわゆる焼け跡闇市時代にネオンはなかった。露店の照明は裸電球かアセチレン灯で、もちろん宣伝とか広告とは無縁である…。
子供の目にもそんな光景が焼き付いていたので、私はことさらネオンに、それも原色のネオンにこだわるのかもしれない。あれは本当に美しかった!
私は毒々しいまでのネオンの色彩についてこう書き記している。「それは陰々たる闇から光まばゆい極彩色の世界へ抜け出た証しであり、灯火管制と停電の日々とおさらばする新しい時代との出逢いを告げるものだった」
あれから五十有余年。青や白の発光ダイオードの普及のせいだろうか、たとえば歳末の六本木ヒルズや新宿南口のサザンテラスの並木の電飾など、シックで幻想的な効果を狙っているようだ。これも時代か。
しかし私にはネオンの色に染まる裏通りを、男も女も色とりどりの紙のトンガリ帽子をかぶって、ひしめくように浮かれ歩いていたクリスマス・イブのあの猥雑な活気が、夢のように懐かしい。