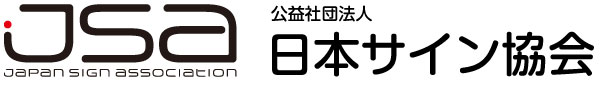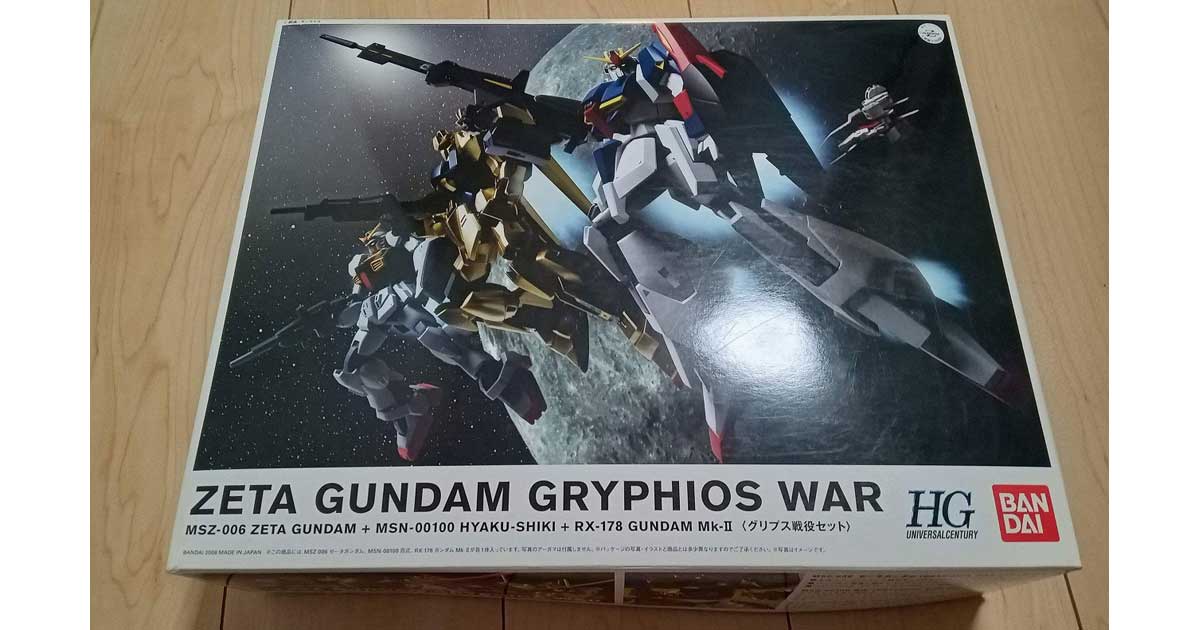皆様こんにちは。今回は私の焼酎の選び方と飲み方をご紹介したいと思います。すでにワインブーム、焼酎ブームも過ぎ去っておりますが日頃の飲み方のご参考になれば幸いです。
鹿児島の焼酎は芋焼酎がメインになりますが酒蔵数はなんと113、銘柄数は2,000以上あります。原料となる芋は黄金千貫をはじめ紅さつま、紫芋、安納芋…そして白麹、黒麹、黄麹、独自の酵母、それぞれの地域の清流、湧き水で発酵・蒸留されます。新潟の清酒と同じように上越・中越・下越と地域、酒蔵が変われば味も変わるのと同じで焼酎も同様です。
本格焼酎のエリアと特徴
鹿児島は地域を大きく分けると薩摩半島の北薩、南薩、大隅、加治木、種子屋久、奄美に分けられます。これからは焼酎選びに地域ごとの大まかな特性をご紹介しますが私の持論ですのでご参考までに。
北薩地区
すっきりした飲み口の中に芋の風味が追いかけてくる。
◎有名銘柄:村尾、さつま島美人、出水に舞姫
南薩地区
どっしりとしたウイスキーのような飲み口、芋の風味も強い、ザ・焼酎!
◎有名銘柄:さつま白波、桜島、貴匠蔵、宝山
大隅地区
さらり、すっきり、ほどよい芋の風味、飲みやすい銘柄が多い。
◎有名銘柄:森伊蔵、魔王、八千代伝、白玉の露
加治木地区
酒蔵によって風味が変わるユニークな焼酎が多い地区。
◎有名銘柄:伊佐美、伊佐錦、侍士の門、アサヒ
種子屋久地区
種子島は安納芋の甘み、ブランデーのよう、トロっとした飲み口。屋久島はすっきりキリッとしながら飲みやすい。
◎有名銘柄:安納、紫、三岳、愛子
奄美地区
黒糖焼酎が多い、黒糖の甘み、ラム酒のようなコクが口にやさしく広がる。
◎有名銘柄:れんと、里の曙、島有泉(与論)
どうでしょう、ご存じの銘柄はいくつありましたでしょうか。
焼酎の飲み方
ロック、水割り、お湯割り、最近は焼酎ハイボール(チューハイ)もありますが、今回は水割りとお湯割りをご紹介します。
水割りはまずグラスに氷を入れ焼酎を6~7割入れます。そのあとマドラーで氷が解けグラスの表面が結露して白くなるまでマドラーで混ぜ、そして割水を注ぎマドラーで1回くるりとすれば完成。この時点で5:5または6:4の比率になりグラス上部は少ししか混ぜていないので少し薄く感じますが徐々に氷が解けてグラスが空くまでおいしく飲めます。注意点は水道水を使わずミネラルウォーター(軟水が理想)、ない場合は水道水を一旦沸騰させた水を使ってください。水道水だとカルキ(塩素)の味が際立ち焼酎の味が変わってしまいます。
次にお湯割りですが、ご存じの通りお湯を4割先にグラスへ入れ、焼酎6割を注ぎます。この時は敢えてマドラーで混ぜず湯と焼酎が自然に対流する様子を見ながら飲んでください。6:4で25度の焼酎がちょうど清酒と同じ15度になります。
最後に「前割り」です。これは焼酎を飲まれる2日前までに仕込みます。焼酎6,水4の割合でペットボトルなどに入れて、日を改めて飲むとさらにまろやかになり旨さが増します。
例えばおでんの具を出汁に入れ1日待つと具に染み渡るのと同じで割っているのに更に美味しくなります。保管は冷蔵庫で。温めても良し、ロックで飲んでも良し。自分好みの銘柄に出会えると晩酌のひと時が楽しみになると思います。
もちろん飲みすぎには注意ですが、自分好みの焼酎を酒屋で探されてみてください。または鹿児島を巡り、飲食店で食事をしたり蔵見学をして多種の焼酎を飲めば、自分の嗜好に合ったブランドにいくつも巡り会うことができるはず。 一度、焼酎を飲みに鹿児島を訪れてみてはいかがでしょうか。五感が刺激され、今までにない感動が得られるはずです。
九州支部 ㈱ニシムラ 西村 剛